中・高・大学受験で合格を手に入れるブログ「中学受験ポータル」の「【オンライン家庭教師】大学受験おすすめランキング!人気6社を徹底比較」にて弊社が運営する忍者英会話の記事が紹介されました。 続きを読む
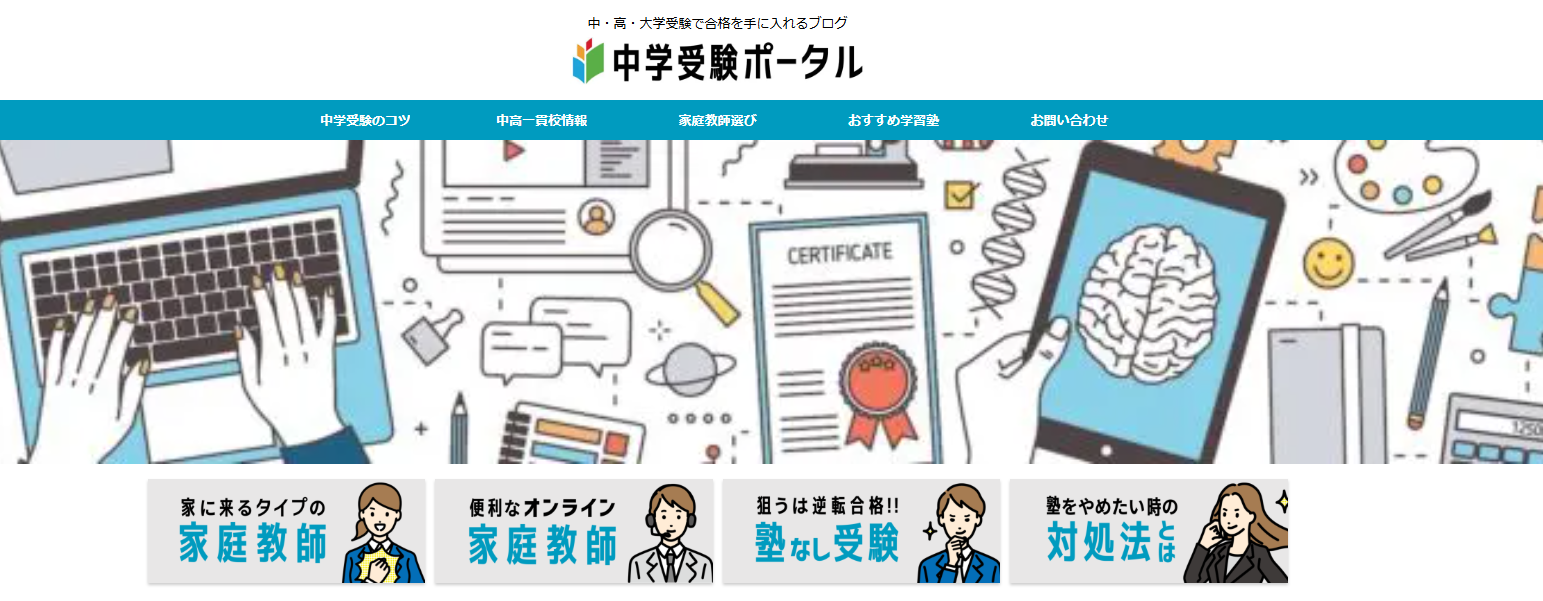
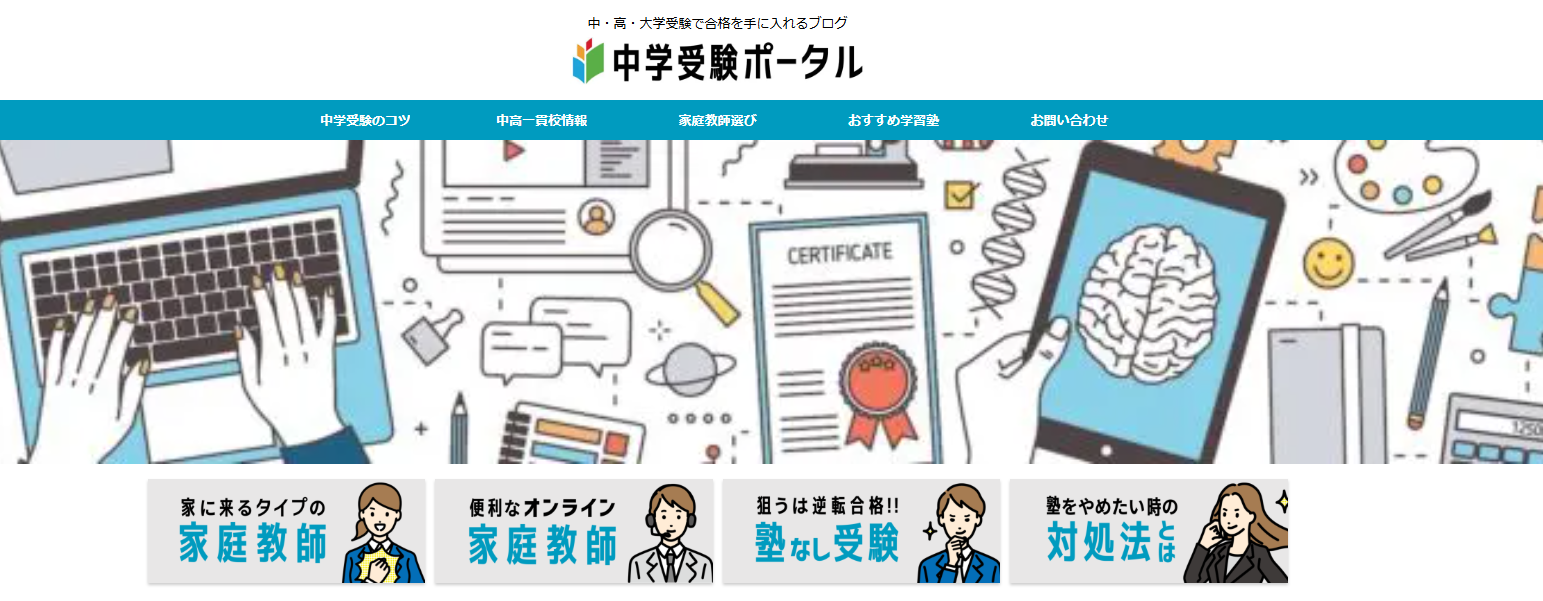
中・高・大学受験で合格を手に入れるブログ「中学受験ポータル」の「【オンライン家庭教師】大学受験おすすめランキング!人気6社を徹底比較」にて弊社が運営する忍者英会話の記事が紹介されました。 続きを読む

プルメリア音楽教室の運営するコラム内の記事「失敗しない習い事選び!スクール・習い事教室&学び情報サイトまとめ」に弊社メディアであるEnglish Hubの記事が掲載されました。

埼玉県の個別指導塾「芝原塾」の「おすすめサイトまとめ」ページにて弊社のWEBメディアである「English Hub」が紹介されました。

総合学習メディア#スタシェアの「【徹底解説】安いだけではなく実力がつくオンライン英会話7選」にて弊社が運営するEnglishHubの記事が紹介されました。
#スタシェアは、塾選び・勉強法・受験情報をわかりやすく届ける学習特化型メディアです。
「自分に合った勉強法がわからない」「塾はどう選べばいいのか不安」――そんな悩みを抱える中学生・高校生・浪人生、そして保護者が、納得して学習に向き合えるようサポートすることを目的としています。
運営には、医学部生や旧帝大生など難関大学に合格した15名以上のメンバーが参加。実体験に基づく勉強法や受験の乗り越え方を中心に、役立つ情報を発信しています。また、予備校講師や保護者など、多様な立場の声も取り入れ、受験生を多角的に支援しています。
受験や勉強の悩みは、検索しても必要な情報にたどり着けないことが多く、孤独を感じやすいものです。#スタシェアでは、過去の自分たちが「本当に知りたかったこと」を厳選してまとめ、迷いや不安を少しでも減らせるよう記事を提供しています。
大学選び・塾選び・日々の勉強法など、学習に関するあらゆる悩みを解決するための情報を発信していますので、ぜひ参考にしてください。
学術的な(アカデミックな)文章には書き方のルールがあります。このルールを英語ではアカデミックライティング(academic writing)と呼びます。学府に提出する文章は、論文であれレポートであれ、所定のルールを踏まえて記述しなくてはなりません。
作成する文書の種類によって体裁は違ってきますが、基礎的な考え方やルールは共通です。アカデミックライティングの基本を踏まえた上で、適格な文章を提出できるようになりましょう。
アカデミックライティングの根本は日本の(日本語の)論文・レポートの書き方にも通底します。特に海外の大学へ正規留学するわけではない方も知っておいて損はありません。
日本語のカタカナ英語表現は、正しい英語表現とは限りません。英語の本来の意味や用法、正しい英語表現を学び直しましょう。
今回の和製英語は「home page 」。
おすすめ関連サービス紹介
株式会社アシストは、中小企業・店舗向けにホームページ制作やMEO対策、アプリ開発などのWeb集客支援を行うデジタルマーケティング会社です。

2025年6月23日、弊社オンライン英会話サービス「Weblio英会話」をご利用いただいている聖学院中学校様にご協力いただき、オンラインレッスンのようすおよび英語授業の見学を実施し、あわせて先生方へのインタビューのお時間も頂戴いたしました!

近年、社会のグローバル化が急速に進む中で、大学教育においてもグローバル人材の育成が重要な課題となっています。
グローバル化が進むビジネス分野では、国境を越えて活躍できる人材が求められる一方、日本国内でも外国人観光客の増加や在日外国人の増加など、日常生活の中でグローバル化を肌で感じる機会が増えてきました。
このような状況の中、文部科学省は「グローバル人材育成推進事業」を立ち上げ、大学教育のグローバル化を推進しています。
グローバル教育に力を入れている大学では、語学教育や留学制度の充実はもちろん、海外からの留学生を多く受け入れることで、日本人学生が日常的に異文化交流を体験できる環境を整えています。
また、海外大学との連携を強化し、国際的な研究交流や学生交流を活発に行うことで、グローバルな視点を持った教育を実践しています。
本記事では、グローバル教育に定評のある大学を厳選し、その特徴や取り組みを詳しく解説します。将来、グローバルな舞台で活躍することを目指す方は、ぜひ参考にしてください!
また、グローバルに活躍したいと考えている方は普段の英語学習についても悩みを持っているかと思います。
弊社メディアEnglishHubの記事「おすすめのオンライン英会話を徹底分析して紹介します!」で総合的・目的別におすすめのオンライン英会話サービスを紹介しているので、こちらもぜひ参考にしてください。
続きを読む

日本人は英語が苦手という認識は皆さん持っていると思います。
一つの指標にしかなりませんが、EF EPIによるランキングで、日本は世界113の国と地域の中で87番目の英語力であるとされています。また、アジア内でみても23ヵ国中15番目です。
PR:成績を上げたい高校生必見!おすすめのオンライン家庭教師をまとめました!

2006年に『どんどん話すための瞬間英作文トレーニング』が発売されてから、英語学習者のあいだで広く知られるようになった「瞬間英作文」。書店には関連書籍が並び、語学スクールのカリキュラムにも取り入れられるほど、未だにその人気は衰えを知りません。
実際に、日本語の文を見て即座に英語に訳すというトレーニングは、英語を瞬時に組み立てる力を鍛える点では非常に有効です。文法や語彙の定着にもつながり、いわゆる「英語脳」の基礎力を作る助けになることは間違いありません。
しかしその一方で、
といった声も少なくありません。
なぜなら、瞬間英作文によるトレーニングは、適切な方法で取り組まなければ、効果が思ったほど現れないことがあります。実際、私が最初に「瞬間英作文」に取り組んだときも、教材の例文はスラスラ言えるのに、実際の会話になるとまったく話せませんでした。そして、こういった「瞬間英作文で効果がない」ことの原因の多くは、「やり方の誤り」や「目的とのズレ」にあります。
そこで本記事では、瞬間英作文のトレーニングに取り組んでいるのに効果が実感できない人に向けて、実際に私がやってみて失敗した方法と、そしてそれを踏まえた上での対策を詳しく解説します。
と感じている方は、ぜひ最後までお読みください。英語が口から自然に出てくる実感を得るための突破口が、きっと見つかるはずです。

社会人になってから英語を学び直そうと決意したものの、いつの間にかやらなくなってしまった――そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。特に仕事や家庭で忙しい毎日を送る社会人にとって、英語学習の習慣化は簡単ではありません。
しかし、なぜ「続かない」のか。その理由は決して意志の弱さではなく、環境や学習設計、心理的な要因にあります。この章では、「社会人 英語 続かない」と感じている方のために、英語学習を挫折してしまう主な理由とその根本的な原因を、具体的かつ体系的に解説します。

赤ちゃんは、どのようにして言葉を覚え、他者と関わるようになっていくのか。
当たり前のように見えるその成長の過程を、科学的に明らかにしようとする学問があります。それが、発達心理学です。
今回お話をうかがったのは、乳幼児の言語獲得や社会性の発達をテーマに研究をされている、今福理博(いまふく・まさひろ)先生。保育や教育の現場にもつながる発達のメカニズムを解き明かしながら、学生たちには「子どものことがわかる保育者・教員になってほしい」と語ります。
研究者として、教育者として、そして絵本の著者として。
子どもの育ちを支えるさまざまな取り組みと、その背景にある思いを、丁寧に語っていただきました。

シャドーイングとは、英語の音声を聞きながら、少し遅れてそのまま復唱する学習法です。聞こえてきた英語をそのまま口に出すことによって、英語の音に対する感覚を磨くと同時に、発音やリズム、イントネーションなどの音声的な要素も習得することができます。
この学習法は、同時通訳の訓練法として知られており、通訳者を目指す人たちがプロの現場でも活用していますが、現在では英語学習者にも広く取り入れられています。
以下に、一般的なシャドーイングの手順を紹介します。
最初はうまくできなくて当然です。特に、初心者のうちは「口が追いつかない」「聞き取れない」という感覚が強いですが、これを乗り越えることで、大きな成長を感じられるようになります。

「海外で誰かの役に立つことがしたい」
そんな気持ちを持ったことのある高校生は、決して少なくないはずです。しかし実際に、世界の現場では何が起きているのか、そこにどう関わることができるのかは、なかなか見えにくいものです。
今回お話をうかがったのは、長崎外国語大学で東南アジアの開発と文化の関係を研究している小鳥居先生。
先生は、インドネシアやカンボジア、タイなどの地域に実際に足を運びながら、現地の暮らしや課題を見つめ、「外から与える支援」ではなく、「中から育つ変化」に関心を持ち続けてこられました。
「現場に行って、自分の目で見ること」「支援とは何かを考えること」
先生の言葉には、国際協力やフェアトレードといった言葉を、現実の人々の暮らしに引きつけて考えるヒントが詰まっています。
研究者として、そして教育者として、学生たちと共に取り組んできた活動の中から、未来を考える手がかりをお届けします。

医療の世界は日々進歩していますが、それでもなお「治療が難しい病気」は数多く残されています。
中でもがんは、今も多くの人の命に関わる深刻な課題です。
今回お話を伺ったのは、宮崎大学で免疫学を専門に研究し、がん免疫療法の新しい可能性を探っている佐藤克明先生。
樹状細胞という免疫の中枢に関わる細胞に注目し、これまでにない治療法の開発に挑んでいます。
しかし、そんな最先端の研究に取り組む先生も、最初から免疫学を目指していたわけではないといいます。
高校生に向けた今回のインタビューでは、専門分野の話だけでなく、「学問との出会い方」や「進路の見つけ方」についても、率直な言葉で語ってくださいました。
続きを読む
日付の書き方のポイント例:「2021年11月8日」の場合、
英語の日付の書き方は、アメリカ式とイギリス式で並び順が違います。例えば「2021年11月25日」は、アメリカ式では「November 25, 2021」、イギリス式では「25 November 2021」の順で記述します。また、「月」や「日」の書き方には複数の表記パターンがあります。
例:「2021年11月8日」の英語での読み方は、November eighth in twenty-twenty-one 。
アメリカ式表記では「11/8/2021」「November 8th, 2021」「November 8, 2021」のように表記します。
イギリス式表記では「8/11/2021」「8th November 2021」「8 November 2021」のように表記します。
PR:【厳選】IELTSの塾ならここ!本当におすすめのスクール徹底比較!

高校生にとって、大学でどのような学問が学べるのかを知ることは、進路選択の大きなヒントになります。連載コラム「大学で学べる学問を知ろう」では、各分野の専門家にインタビューを行い、学問の魅力を探ります。
今回は、「国際教育」を専門とする宮城教育大学の市瀬智哉先生にお話を伺いました。
✔ 国際教育とはどのような学問なのか?
✔ 日本と海外の教育にはどのような違いがあるのか?
✔ これからの時代に必要な学びとは?
国際社会で求められるスキルや、高校生が今からできることについて、先生の研究をもとに詳しく解説していただきました。
続きを読む

企業と環境問題、地域の活性化、そして伝統産業の再生——。
一見バラバラに見えるこれらのテーマを、ひとつの大きな視点でつなげながら探究を続けているのが、東京富士大学 経営学部の藤森大祐教授です。
藤森先生は、公害という社会問題から企業の環境対策に目を向け、地方の自然との出会いをきっかけに「地域の持つ力」に気づき、やがて都市・新宿に残る染色文化の継承や、サッカークラブとの地域連携など、多岐にわたるテーマに取り組んでこられています。
今回のインタビューでは、「環境とどう向き合うか」から始まった先生の研究の歩みと、学びの中にある“人とのつながり”や“問い続ける面白さ”についてお話を伺いました。
進路を考える高校生の皆さんにとって、学問との出会いがどんなふうに広がっていくのか。そのヒントが、きっとこの対話の中にあるはずです。
続きを読む
英語では、文章中の2つの単語が連結して発音が変わる現象(いわゆるリエゾン)がよく生じます。リエゾンは、英語では linking(リンキング)という呼び方のほうが一般的です。
リエゾン(リンキング)は、英語の文章レベルの発音に関わる大事な要素です。大まかな要領は早々に把握してしまいましょう。

高校の授業ではあまり耳にする機会のない「平和学」。けれども、世界で起きている戦争や社会の対立、私たちの身近にある差別や分断といった問題に向き合ううえで、この学問は非常に重要になります。
帝塚山大学で国際法と平和学を教える末吉洋文先生は、学生たちとともに戦争遺跡をめぐるフィールドワークを行ったり、小学校での平和学習の教材づくりに取り組んだりと、学問と社会をつなげる実践を続けてきました。
今回は、高校生に向けて、平和学とはどんな学問なのか、どのような魅力があるか、具体的な活動や経験を交えながら語っていただきました。
続きを読む